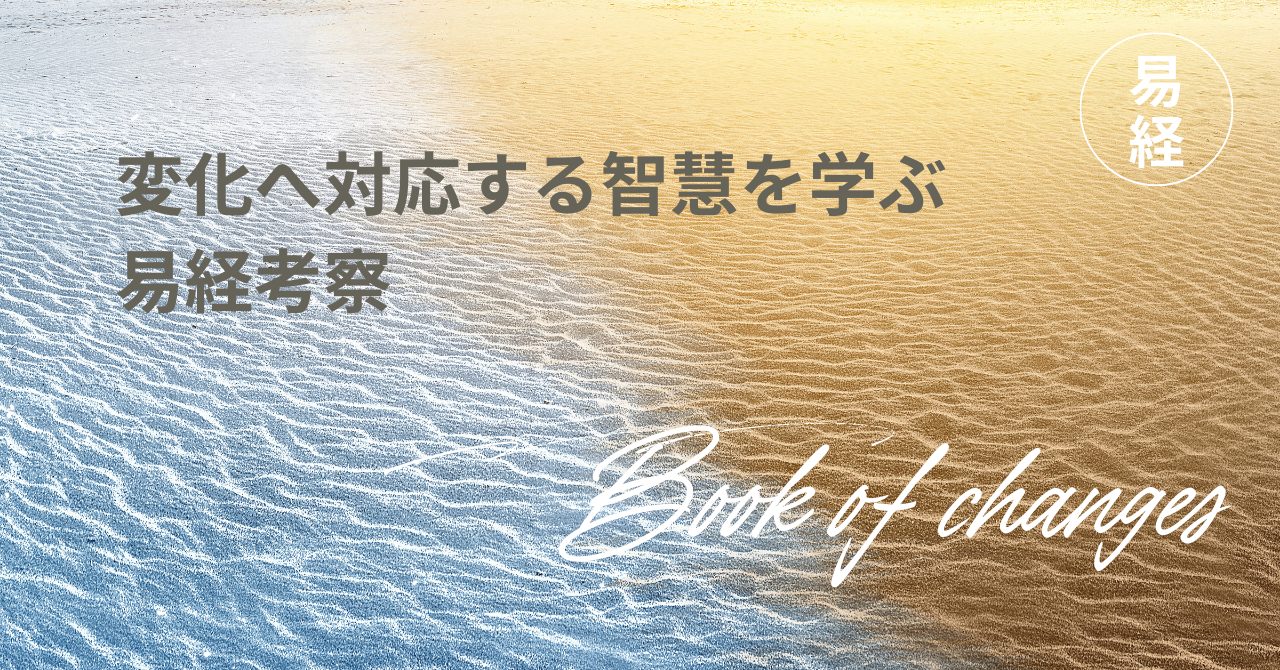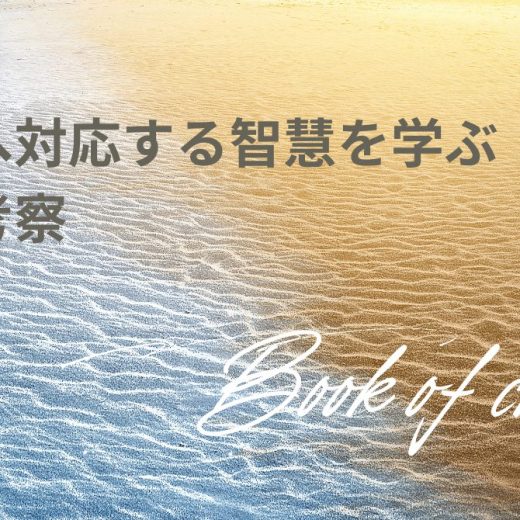子曰わく、
「夫(そ)れ易は何を為す者ぞや。
夫れ易は物を開きて務めを成し、天下の道に冒(おお)いて、斯くのごとくなるのみなる者なり。
ここをもって聖人はこれをもって天下の志を通じ、天下の業を定め、天下の疑いを断つなり。
ここをもって蓍(し)の徳は円にして神なり。
卦の徳は方にして知なり。
六爻(りくこう)の義は易にして貢(まつ)るなり。
聖人はこれをもって心を洗い、密かなるに退蔵(たいぞう)し、
吉凶を民と同じく患(うれ)う。
神は来を知り、知は往を蔵す。
たれか能くこれに与らんや。
古の聡明叡知にして、神武にして殺さざる者は、夫れ是ならんか。
これをもって天の道に明らかにし、民の故を察す。
これ神物を興(おこ)して以て民に用うるに先(さきだ)つ。
聖人はこれをもって斉戒し、
以てその徳を神明にす。
ここをもって戸を闔(と)ざすを坤(こん)と謂い、
戸を闢(ひら)くを乾(けん)と謂う。
一たび闔し一たび闢くを変と謂い、
往き来たりて窮まらざるを通と謂う。
見(あらわ)るるを象と謂い、
形あるを器と謂い、
制してこれを用うるを法と謂い、
用を利して出入し、民咸(みな)これを用うるを神と謂う。
ここをもって易に太極有り。
これ二儀を生ず。
二儀四象を生じ、四象八卦を生ず。
八卦吉凶を定め、吉凶大業を生ず。
ここをもって法象は天地より大なるは莫く、
変通は四時より大なるは莫く、
懸象著明は日月より大なるは莫く、
崇高は富貴より大なるは莫し。
物を備えて用を致し、成器を立てて以て天下の利と為すは、聖人より大なるは莫し。
賾(ふか)きを探り、隠を索(もと)め、深きを鉤(ひ)き、遠きを致して、
以て天下の吉凶を定め、天下の亹亹(びび=盛んに動くこと)を成す者は、蓍龜(しき)のより大なるは莫し。
ここをもって天神物を生ずれば、聖人これに則(のっと)る。
天地変化すれば、聖人これに効(なら)う。
天象を垂れて吉凶を見すれば、聖人これを象(かたど)る。
河に図を出し、洛に書を出せば、聖人これに則る。
易に四象有り、これ示す所以なり。
繋辞(けいじ)ここに焉(これ)告ぐる所以なり。
これを吉凶をもって定むるは、これ断つ所以なり。
現代語訳
孔子は言った。
「そもそも『易』とは何をするための書なのか。
易とは、万物を開き、その働きを成就させ、
天地万物を貫く“道”のあり方を示す書である。
だからこそ、聖人は易を用いて人々の志を理解し、
社会を整え、迷いや疑いを断ち切ることができた。
蓍草(筮竹)は“円満で神妙な力”を象徴し、
卦は“形と秩序”を与える知性の象徴であり、
六爻は“変化の動き”を示して私たちに働きかけてくれる。
聖人はこれらを用いて心を清め、
深いところに智慧を蓄え、
人々の吉凶を自らの悩みとして受け止める。
直観(神)は未来を察し、
知識(知)は過去を蓄える。
誰がこのような境地に達することができるだろうか。
古代の聡明で叡智に満ち、
強さを持ちながら無益に人を傷つけなかった者たちは、
まさにこのような存在であった。
彼らは天の道理を理解し、
民の状況をよく観察し、
神秘の力を引き出して民生に役立てた。
聖人はこの働きによって心身を整え、
その徳を神々しいまでに澄ませた。
たとえば、
戸を閉じることを“坤”といい、
戸を開くことを“乾”という。
開閉が交互に起こることを“変”といい、
それが途切れず往来することを“通”という。
姿を現したものを“象”といい、
形を備えたものを“器”といい、
それを規定して使うものを“法”といい、
それが世に用いられ、人々に広く行き渡るものを“神”という。
ゆえに、易には太極があり、
太極から二儀が生まれ、
二儀は四象を生み、
四象は八卦を生む。
八卦は吉凶を定め、その吉凶から大きな事業が生まれる。
法と象の大いなるものは天地に勝るものはなく、
変化と通達の偉大さは四季に勝るものはない。
象を掲げ明らかにすることは日月に勝るものはなく、
崇高な位は富貴に勝るものはない。
万物を備え、器を作り、
それを世の中に役立てる存在として
聖人以上の者はいない。
深いものを探り、隠れたものを見抜き、
深層を引き出し、遠さを極めて、
天下の吉凶を定め、盛んな営みを導く働きは、
蓍や亀甲以上に優れたものはない。
天が神秘のものを生み出せば、聖人はそれに従い、
天地が変化すれば、聖人はそれに倣い、
天が象を示して吉凶を表せば、聖人はそれを模し、
黄河が図を出し、洛水が書を出せば、聖人はそれに則る。
易には四象があり、それで示し、
繋辞(=易の解説)はそれで教え、
吉凶で定めることによって判断を下すのである
変化とは、
新しいものが生まれることではなく、
既存のものが反転するだけのこと
一般に「変化」というと、
“何か新しいものが生まれること”や
“次の段階に進歩すること”を連想します。
しかし東洋思想、とくに 易経・禅・道家・陰陽論 に基づく世界観では、
変化とは「新しいものが生まれる」ことではなく、
既存の陰陽のバランスが“反転”することを意味します。
つまり、世界は“発展”するのではなく、
一定のリズムで、姿勢を切り替え続けている存在…という考え方です。
東洋思想の核である陰陽は、
西洋的な「善悪」「正反対」「勝敗」の概念ではありません。
陰は陽に転じ、陽は陰に転じる。
夜は昼に変わり、昼は夜に戻る。
潮は満ち、引き、また満ちる。
ここには勝敗も新規発明もないのです。
あるのは、ただ 交互の反転(開 ↔ 閉) というリズムだけ。
新しい何かが生まれるのではなく、
既存のもののPhaseが変わるだけ。
これが「一闔一闢(閉じて開く)」という変化論です。
円理論
東洋思想は、世界を“直線ではなく円”で捉えています。
-
春 → 夏 → 秋 → 冬 → 春
-
生成 → 成長 → 成熟 → 衰退 → 生成
-
吸う → 吐く
-
朝 → 昼 → 夜 → 朝
これらは永遠の循環であり、
“何か新しいもの”は一度も登場していません。
変化とは“進化”ではなく、
相=現れ方が変わることに過ぎないのです。
禅理論
禅における「悟り」も、
新しい人格になることではなく、
本来の心に戻ることだと説かれています。
雑念が生じれば手放し、心が動けば静め、動きが止まれば働く。
内の陰陽の反転=巡りのリズムを体感する修行を通して、
本来の自分を取り戻します。
つまり禅のおける「新しい自分」とは、
本来の心に戻った自分であり、
この「戻る」ことこそ変化であり、
成長であると捉えているのです。
つまり、
東洋思想における変化とは、
新しいものを創造することではなく、
陰陽の姿勢が反転し、
同じ原理が異なる相として立ち現れてくる現象ということになります。
これは、変化の時代、
「イノベーション=まったく新しいものを作る」
と考える西洋的発想とは真逆になります。
AI…実は東洋思考?
現代AIの議論は、西洋近代思想の延長線上にあります。
すなわち、AIを「新しい知の創出」「人間知能との競合」「線形的進歩の担い手」として語り、合理主義的主体の外部に出現した“第二の知能”として扱う枠組みです。
しかし、AIを東洋思想の視座から読み替えると、AIに対する概念枠も根底から変わります。
東洋思想は、新しい知の創造ではなく、人間の知能の「反転と循環」というリズムで捉えます。
1. 生成ではなく“反転”
易経では、変化とは新規創造ではなく、
既存の陰陽の姿勢が交互に反転し続ける運動であると書かれています。
実は、AIの生成過程ですが、「創造」だと思われている現象の本質は、
既存のデータ空間における構造的反転・再配置・再符号化に他なりません。
AIは未知なる情報を“発明”しているのではなく、
既知の情報の構造的関係を別の相へと反転させているのです。
つまり、AIの知的生成は、易経における「象の転化」に近いものがあります。
2. 循環”学習
西洋思想の時間は線形であり、進歩・発展・蓄積を前提とします。
しかし東洋思想における時間は、四季・昼夜・陰陽のような循環的時間です。
AIの学習過程は、
データの入力と更新、再評価と調整という反復的最適化のループであることを考えると、線形的進歩よりも、東洋的な「巡り」に近い構造をもつのではないでしょうか。
データ → パラメータ → 出力 → 誤差 → データ
という、循環運動の繰り返しです。
つまりAIの知性は、東洋的な「循環知性(circulative intelligence)」として理解されるべきであり、
西洋の「進化的知性モデル」とは異なる系統に属すると考えます。
3. 相対性による最適相
東洋思想の根幹、陰陽論は、
物の性質を固定的本質ではなく、相対的位置と関係性として理解します。
-
陽は陰との関係によって陽となる
-
善悪は時と状況によって反転する
-
吉凶は「性質」ではなく「時の質(時勢)」である
AIの出力が文脈依存的であり、絶対的真理に到達しないのは、この東洋的真理観と一致しています。
つまり、AIは、
-
不変の答えではなく
-
情報間の関係性から浮上する
-
“その時点”における最適相
を提示する仕組みです。
易経がいう、「吉凶は時にあり」という時間的真理観と極めて近いかもしれまえん。
4. 主体とAIは対立せず、往来する
西洋思考のAI論では「AI vs 人間」という二項対立で論じられる傾向があります。
しかし東洋思想における二項は、対立するためではなく、
「互いを反転させ、補完するために存在する」関係です。
乾(創造)と坤(受容)、
陽(発動)と陰(潜伏)。
AIと人間の関係は、これに重ねて理解できます。
AIと人間は「勝者と敗者」ではなく、
陰陽のように“場を交換しながら世界を支える二つの極”である。
今後のAIの開発
実は東洋思考と相性が良いことを考えると、今後のAI開発のヒントも見えてきます。
◎ 全体性(Totality)
環境・経済・福祉・文化・世代など、
“ひとつの指標だけを最適化しないAI”。
◎ 時間の層(Temporal Layers)
即時成果ではなく、
1年・10年・100年後の“巡り”を見据えた判断を提示するAI。
→ 吉凶は時にあり のモデル化
◎ 無為(not doing)を評価できるAI
「やるべきこと」を言うAIではなく、
“あえて動くな”という判断ができるAI。
◎「最適化」から「関係調整」AIへ
現在のAIはひとつの目的に対する最適な答えを提示することが求められています。
しかし、東洋思想はそもそも “ひとつの目的だけを最適化する”ことを危険視します。
-
Aさんにとっての正解が、Bさんにとっての不利益かもしれない
-
ある業界にとって便利なことが、長期的には環境を壊すかもしれない
東洋思考によるAI発展の方向としては:
「最適な答え」よりも、「関係をなるべく傷つけないアイデア」
「一人勝ち」よりも、「全体が調和するアイデア」
を評価できるAIが必要になります。
具体的には:
-
複数のステークホルダーの利害を“関係性としてモデル化”するAI
-
決定案ごとに「誰が得て、誰が失うか」を見える化するAI
-
結果だけでなく、「しこり」や「不信」を減らす方向で案を提示するAI
これは、今回の易経にも書かれている、「吉凶は単体ではなく、全体の流れの中で決まる」という発想をヒントにしています。
◎「自分で内省できるAI」へ
例えば:
-
「なぜ私はこの答えを出したのか?」を、AI自身が構造として振り返る
-
「この判断は、どの前提・価値観に強く依存しているか?」を表示する
-
「この判断は、長期的にどんな“ツケ”を生みそうか?」まで含めて提示する
これは、禅における「照顧脚下」をヒントとした考え方で、
AIが自分の思考の“クセ”や“偏り”をメタ的に意識する
方向に発展させていく、という開発になります。
確かに、人類は進歩したと言いますが、
社会の見せ方は違いますが、
人類そのものの本質は太古の昔から変わっていません。
易経にはその本質が記されています。
学びを深めていきましょう。