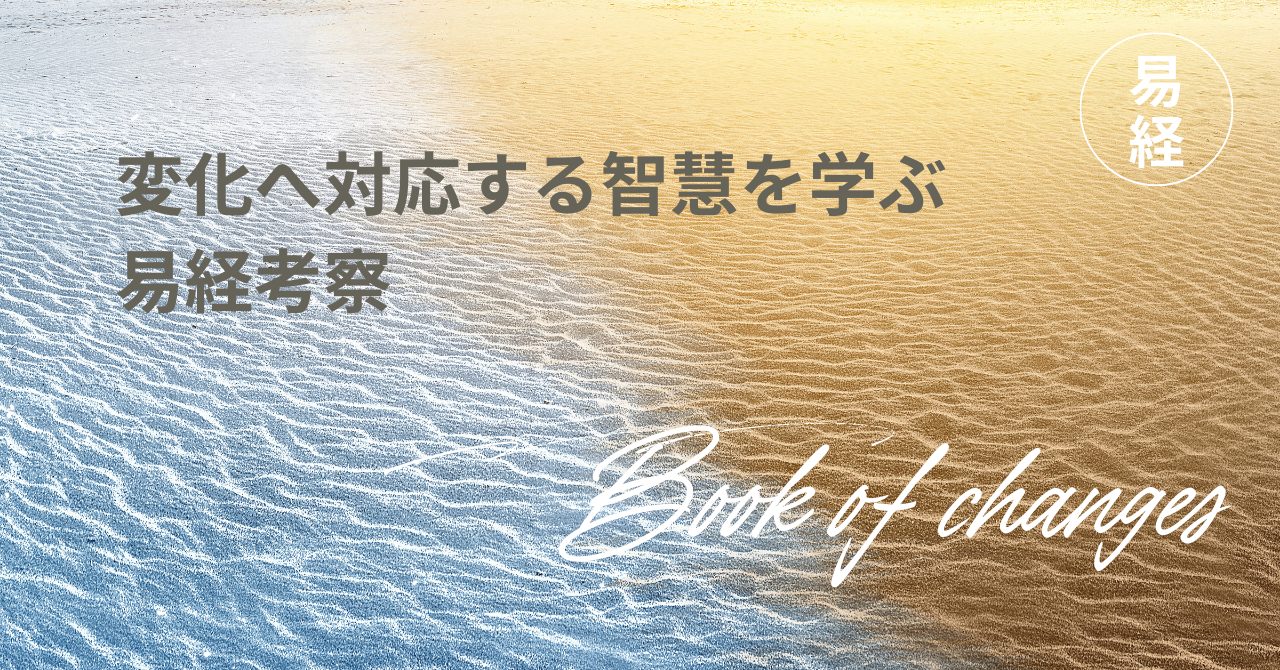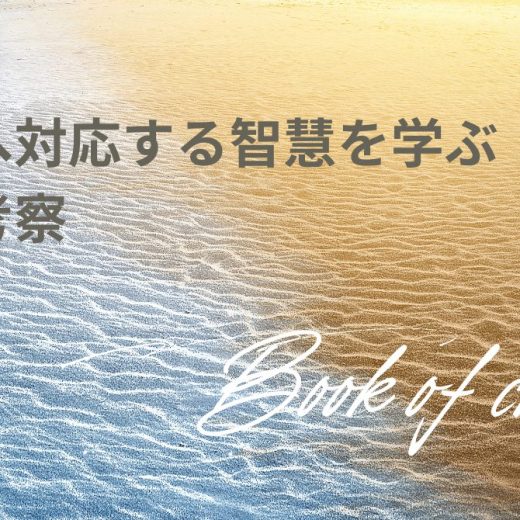読み下し文
子曰わく、
「それ易とは、何をなす者ぞや。
易は、物を開きて務めを成し、天下の道に冒(おお)いて、かくのごとくなるのみなる者なり。
ここをもって、聖人はこれをもって天下の志を通じ、天下の業を定め、天下の疑いを断つなり。」
ここをもって、
蓍(し)の徳は円にして神なり。
卦の徳は方にして知なり。
六爻(りくこう)の義は、易にして貢(まつ)るなり。
聖人はこれをもって心を洗い、密かなるに退蔵し、吉凶を民と同じく患(うれ)う。
神は来(らい)を知り、知は往(おう)を蔵す。
たれか能くこれに与らんや。
古の聡明叡知にして、神武にして殺さざる者とは、夫れ是ならんか。」
現代語訳
孔子は言った
「そもそも『易経』とは何のためのものか?
『易経』とは、物事の本質を明らかにし、世の中の務めを成し遂げるための道具。
天と地のあらゆる道を包み込んでいる大きな力になるもの。
故に、聖人(賢者)は『易』を使って、
・人々の願いや志を理解し、
・社会の仕事や仕組みを整え、
・誰もが悩む“わからなさ”を解消できたのです。
そこで用いた筮竹とは、
-
筮竹のカタチそのものは、“丸くて神秘的”。
-
卦(け/形にする記号)の性質、“四角くて知性的”。
-
それぞれの線(爻/こう)は“変化をとらえて全体に貢献する”。
聖人はこれらを使って、
自分の心を清め、
深く考える場所にその知恵はしまっておき、
人々と一緒に吉や凶の運命を受け止めていく。
“神のような存在”は、これから起きることを知り、
“知”の力は、すでに起きたことを記憶する。
いったい誰がこれほどの力に関われるだろうか?
本当に賢くて深い知恵を持ち、人を傷つけることがない人物、
まさに聖人とはそういう存在ではないだろうか。
「円・方・動」は東洋思想の三位一体の原理
東洋思想を貫く枠組みとは、「天・地・人」の三才論。
天は根源的原理、地は形と秩序、そして人はそのあいだを生きる存在…。
東洋思想の原理なので、『易経』の三層構造:蓍(円)・卦(方)・六爻(動)は、禅思想における“悟りの構造”とも深く連動しているのです。
○「円」- 蓍の徳
蓍(し)は占筮に用いる蓍草の茎ですが、その本質は単なる道具ではありません。
蓍の操作によって立ち現れるのは、偶然性を通じて顕現する宇宙の“兆し”であり、それは形をもたず、分節化されず、包括的。
「円」という語は、この“未分化の全体性”を象徴し、まさに三才論でいう 「天」 の働きに重なります。
禅の円相(○)が象徴するのは、分節化以前の純粋な存在の自己であり、天が示す根源的な無限性。
蓍が“偶然”という名の必然を通して兆しを受け取るのは、人為を離れ、心が「円」に開かれているからこそ可能となる作法なのです。
□「方」- 卦
卦のもつ 「方」 は、世界に秩序・構造・区分を与える働きです。
これは三才論の「地」に相当し、禅でいえば、戒律・型・作法といった“形式”的側面に通じます。
円相に象徴される無分別の世界がそのまま日常に表現されるためには、一定の「方(かたち)」が介在する必要があります。
『易経』における卦は、宇宙の流れを、人間の知が読み取れる骨格に整える装置であり、禅の修行体系もまた、悟りを具体的な行為として地上に定着させるための“方”として機能します。
× 六爻
六爻が象徴する 「動」 は、人が生きる時間の流れそのもの。
六爻は初爻から上爻までの六段階を示し、発生・成長・成熟・衰退・転換といった“変化のプロセス”を描いています。
これは構造としての卦を時間の中で展開させる働きであり、三才論の 「人」に相当、
人は天と地の間に生き、変化を経験し、判断し、選択していく存在です。
禅においては、禅の実践における「行(ぎょう)」を意味します。
禅では、悟りは静止した概念ではなく、“今この瞬間”の行為として現れるます。
つまり、動くたびに悟りが更新される実践的存在論。
六爻が示す変化の連続性は、まさに「動中に静あり」「一挙手一投足が仏法」という禅の核心と呼応します。
このように見ると、蓍・卦・六爻は単なる占筮技法ではなく、
天の根源(円)を地の秩序(方)へ、そして人の行為(動)へと落とし込む哲学的モデル。
この哲学モデルを、
易は宇宙の変化を円→方→動へと読み解く体系、
禅は人間の存在を円→方→動へと体現する体系
として、哲学展開しています。
方向性は異なりますが、
易が「変化の法則」を抽象化したOSであるとすれば、
禅はそのOSを“身体の側から直接起動する”実践の方法論
易が“宇宙を読む”方法を提供し、
禅が“宇宙をそのまま生きる”方法を提供しています。
東洋思想を体得したリーダーとは?
東洋思想の原理に精通したリーダーとは、
どのような存在なのだろうか。
それは、
タイミング判断(易)× 内的安定性(禅)
に卓越したリーダー像。
今日のビジネス書は、意思決定のスピードや論理性を強調することが多いですが、
東洋思想が扱ってきたのは、より微細で、より深層にある能力—
「間合い」「気配」「絶妙なタイミング」「空気の管理」といった、
欧米型マネジメントではうまく説明しきれない領域です。
たとえば、
会議であえて“間”を置くのは、禅の「動」。
そこで作られる沈黙は、相手の心を開き、場の気配を整え、
言葉よりも多くの情報を浮かび上がらせる働きがあります。
発言のタイミングを読むのは、六爻が示す「動」の読み取りに近い。
まだ早い、もう遅い、この瞬間なら刺さる——
その判断は、状況の変化を細やかに感じ取る敏感さによって成立するのです。
方針を明確に骨格化する行為は、卦の「方」。
全体の構造をくっきりと描き、
誰がどの役割で動くのかを“形”として示すことがリーダーの軸となります。
そして、大局を見失わない姿勢は、蓍の「円」。
目先の利益や感情に揺れず、
広い視野で物事の流れを捉え続けることが、
チームの安心感と方向性を同時に生み出すのです。
これらがひとつの身体感覚として統合されたとき、
はじめて“東洋的リーダーシップ”は生まれます。
それは技法ではなく、世界の捉え方そのもの。
易が「変化の時」を読み、
禅が「今の自分」を安定させる。
この両輪を知徳として習得した
リーダーの言葉や行動は、自然と人を動かす力を帯びるのではないでしょうか。
まさにこのようなリーダーこそが、混迷する時代、必要だと思うのです。