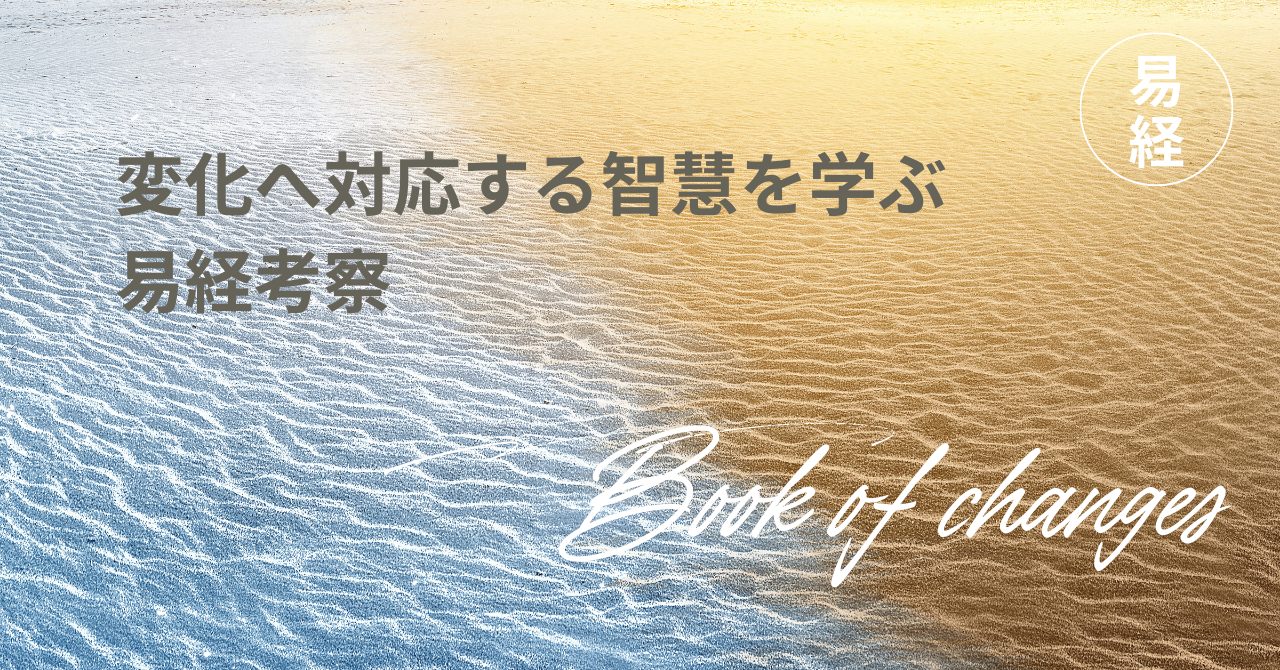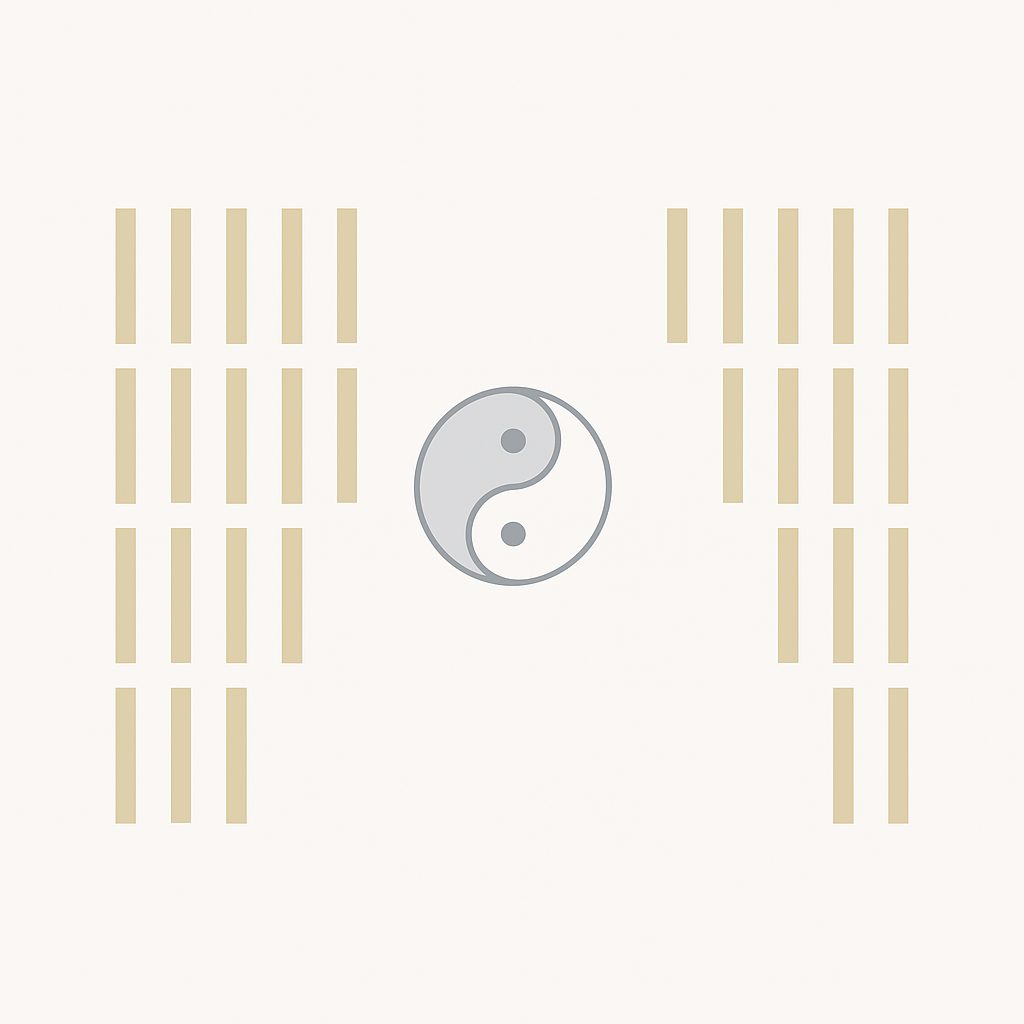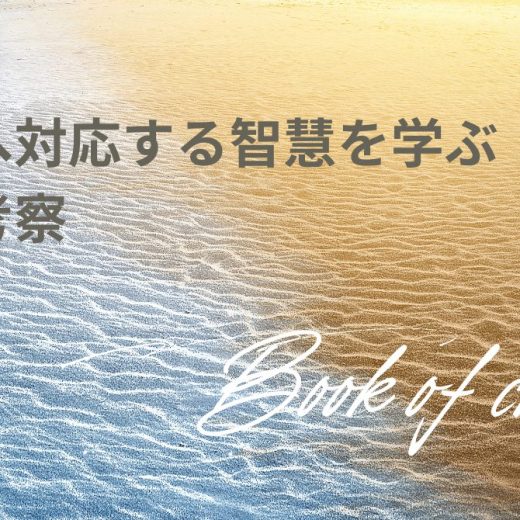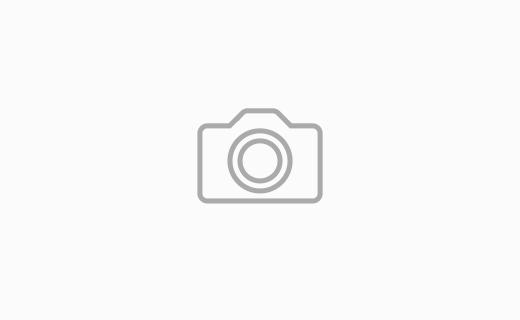原文:
天は一、地は二。天は三、地は四。
天は五、地は六。天は七、地は八。天は九、地は十。
天の数五、地の数五。五位あい得て、各々の合有す。
天の数二十有五、地の数三十。
凡そ天地の数、五十有五。此れ以て変化を成し、鬼神を行うなり。
大衍の数五十、その用は四十有九。
分かちて二と為し以て両を象り、一を掛けて以て三を象る。
之を四に揲(く)みて以て四時を象り、奇を扐(ろく)に帰して以て閏を象る。
五歳にして再び閏あり、故に再び扐して後に掛く。
乾の策、二百一十有六。
坤の策、百四十有四。
凡そ三百有六十は、期の日日に当る。
二篇の策、万有一千五百二十は、万物の数に当るなり。
是の故に、四営して易を成し、十有八変して卦を成す。
八卦にして小成し、引きてこれを伸ばし、類に触れてこれを長ずれば、天下の能事畢(おわ)る。
道を顕し、神の徳行す。是の故に酬酢に与(あずか)り、神を祐くるに与るべし。
子曰く、「変化の道を知る者は、その神の為す所を知るか。」と。
現代語訳
天には一・三・五・七・九という奇数があり、地には二・四・六・八・十という偶数があります。
天の数は五つ、地の数も五つ。五つの位置が互いに調和し、それぞれ対応します。
天の数は二十五、地の数は三十、合わせて五十五。
この天地の数によって、森羅万象の変化が生まれ、鬼神の働きが行われるのです。
「大衍(たいえん)」の数は五十、そのうち実際に使うのは四十九です。
これを二つに分けて陰陽の両儀を表し、一つを脇に置いて三才(天地人)を象ります。
さらに四本ずつ数えて四季を表し、余りを脇に置いて閏月を象ります。
五年に二度の閏があるので、二度余りを置いてから一を掛けるのです。
乾の卦の策(竹の数)は二百十六、坤の卦の策は百四十四。
合わせて三百六十は、一年の日数に対応します。
二篇全体の策は一万一千五百二十あり、これは万物の数に対応します。
こうして四度の営みによって易が成り、
十八の変化によって卦が生まれます。
八卦は小さな完成であり、これを引き伸ばし、類に及ぼして広げていけば、天下のあらゆる営みが尽くされるのです。
道を明らかにし、神のような徳と行いを示すために、人の応酬(やり取り)にも使え、神を助けることにも活用できます。
孔子は言いました――
「変化の道を理解する者は、神の働きを知ることができる」と。
数理的解釈
天地を表す数は、奇数(陽)と偶数(陰)に分けられます。
天数(奇数)=1+3+5+7+9=25
地数(偶数)= 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30
天地を合わせると:
天地の数=25+30=55
55 =「森羅万象の秩序を含む全体数」
2. 大衍の数
「大衍の数」は 55 → 50 に縮減されます。
55−5=
3. 50から49へ
50本の筮竹のうち、1本を脇に置きます。
50−1=49
-
残した「1」 → 太極(宇宙の根源・不可視の原理)
-
操作する「49」 → 陰陽・四時・閏を象徴する有限世界
4. 陰陽・四時・閏
49本を用いて操作を繰り返すときのルール:
-
二分して 両儀(陰陽) を象る。
49 → (a,b), a+b=49
-
片方から1を取り出し、三才(天地人) を象る。
a → a−1, 1 → 脇に置く
-
残りを「4」で割り、余りを脇に置く(四季+閏)
a−1を4で割ったときのあまりを r1とします。
bを4で割ったときのあまりを r2とします。a - 1 = 4 ×□+r1 (0≤r1≤3)
b= 4 ×△+r2 (0≤r2≤3)余りの合計 = r1 + r2
▶この余りが「閏月」を象徴し、五年に二度の調整(再び余りを加える)が行われます。
5. 天地の策と日数
乾・坤それぞれの「策(竹の数)」は定められています:
乾の策=216, 坤の策=144
▶一年の 360日
6. 二篇全体の策
さらに全体では:
360×32=11,520
▶ これは「万物の数」を象徴するとされます。
7. 卦の生成
四度の営みと十八の変化を経て:
4×18=72(卦生成の数理過程)
最終的に八卦(基本セット)が展開され、64卦へと拡張されます:
数式(まとめ)
天数=25, 地数=30
天地の数=55(宇宙の全体秩序)
55−5=50(大衍の数)
50−1=49+1(有限世界と太極)
216+144=360(一年の日数)
2×360×16=11,520(万物の数)
8×8=64(卦の完成)
大衍筮法の実際手順と意味
1. 大衍の数五十、その用四十九
-
「大衍の数五十」とは、筮竹(細い竹の棒)の数を50本用いることを指します。
-
ただし、最初に1本を脇に置くため、実際に操作するのは49本です。
-
脇に置かれた1本は 「太極」=天地の根本原理 を象徴します。
2. 2つに分けて両儀を象)
-
49本の竹を適当に左右2つに分けます。
-
左右は 陰と陽(両儀) を象徴しています。
3. 一を掛けて三を象る
-
左右のどちらかから1本を取り、脇に置きます。
-
この「1本」は 天地人の三才(天・地・人)の「人」を表します。
4. 4で数えて四季を象る
-
残った竹を「4本ずつ」取り分けます。
-
4で割り切れずに余った数(1~4本)が出ます。
-
これは 四季の循環 を象徴しています。
5. 余りを脇に置いて閏を象る
-
余った数(1~4本)を脇に置きます。
-
これは 閏月 を象徴します。
-
暦の調整のように、余りは宇宙の秩序を整えるものとされます。
6. 暦では五年に二度、閏月がある。そのため、筮竹の操作でも余りを二度脇に置いてから再度掛ける
-
五年に二度閏月があるように、同じ操作を3回繰り返します。
-
その結果、1回目の操作では必ず4本または8本が取り除かれます。
-
こうして次第に数が減っていき、最終的に「6・7・8・9」という数が得られます。
7. 数の意味(爻の生成)
-
出てくる数は 6・7・8・9 のいずれかです。
-
6 = 老陰(陰が極まって変化する爻)
-
7 = 少陽(陽の若い爻)
-
8 = 少陰(陰の若い爻)
-
9 = 老陽(陽が極まって変化する爻)
-
-
この数を6回積み重ねることで、六爻の卦(=易卦)が完成します。
まとめ(大衍筮法)
-
50本の筮竹 → 宇宙の全体性(太極)を象徴。
-
操作を3回繰り返す → 天地自然の秩序(陰陽・四季・閏)を再現。
-
最終的に得られる数(6・7・8・9) → 卦を構成する爻を決定。
-
これによって 天地万物の変化を象徴する卦 が立ち、その卦をもとに占断を行う。
解説
①天の数五、地の数五。五位あい得て、各々の合有す。
-
天の数五
天には「5つの数(奇数:1・3・5・7・9)」がある。
→ 天は「陽=奇数」で表されます。 -
地の数五
地にも「5つの数(偶数:2・4・6・8・10)」がある。
→ 地は「陰=偶数」で表されます。 -
五位あい得て
天の5つ(奇数)と地の5つ(偶数)が「位置を得て、互いに対応する」。
つまり、1↔2、3↔4、5↔6、7↔8、9↔10 のように、陰と陽がペアを組む。 -
各々の合有す
そのペアごとに「合わさって一体」となる。
陰と陽が対になって、はじめて世界の根源的な数(天地の運行の基礎)が完成する。 - つまり、陰陽それぞれ5つずつで、それが向かいあって十干を構成している。
-
天の数(奇数)=陽 → 1・3・5・7・9
-
地の数(偶数)=陰 → 2・4・6・8・10
これをペアにすると:
-
1(甲・陽木) ↔ 2(乙・陰木)
-
3(丙・陽火) ↔ 4(丁・陰火)
-
5(戊・陽土) ↔ 6(己・陰土)
-
7(庚・陽金) ↔ 8(辛・陰金)
-
9(壬・陽水) ↔ 10(癸・陰水)
-
天の5つの数と、地の5つの数が向かい合ってペアになり、すべてを合わせて宇宙が成り立つ
②宇宙の完全数=55
-
天数(奇数)= 1+3+5+7+9=25
-
地数(偶数)= 2+4+6+8+10=30
-
合計 = 55
「55」 とは、天地を合わせた宇宙の「全体の数」、つまり、森羅万象を成立させる基盤となる原理の数です。
③人間が操作できる世界=50
55は「宇宙全体の秩序」を表す理論数、つまり、人間を超えた宇宙の全秩序そのもので、完成された完全数であるため、この数字は人間には扱えない=鬼神の数としたのです。
「凡そ天地の数、五十有五。此れ以て変化を成し、鬼神を行うなり。」
そのため、人間が扱える宇宙の姿として「50」を扱うことにしました。
▶なぜ5を抜いたのか?
これは、古来より議論されてきた難問です。
賢人達が考えてきた考察はこうなります。
解釈① 五行を象徴する「5」を残した
-
天地の数55のうち、「5」を削って50にしたのは、
五行(木・火・土・金・水) を象徴するものを根源に留めたからだ、という説。 -
五行は万物の循環原理なので、それを「人間が手を触れられない聖なる5」として差し引いた。
-
結果、残りの50を用いて「循環する世界(四季・陰陽の運行)」を扱った。
解釈② 「完全数55」を人が扱いやすい「円満数50」に変えた
-
古代中国では、10や5は区切りのよい完全数と考えられた。
-
55は大きすぎて直接操作できないので、5を引いて「50=大衍の数」として整理した。
-
つまり、人間が把握可能な秩序に落とし込むための抽象化。
解釈③ 天地の「運行」と「調整(閏)」の違い
-
55は「天地の運行すべて」(暦の全体像)
- 実際の暦は閏を入れて調整するため、その調整分を「5」として削り、50にした。
暦学的視点からみると、自然への畏怖をこめ、完全なる宇宙から1つの小宇宙である5行の5を差し引いたという、解釈①が該当しているように思います。
④大衍:天地自然の変化の数理体系
-
50からさらに1を除いた → なぜか?
-
残された「1」は、太極(根源・不可視の原理) を示す。
-
操作する「49」は、有限の秩序(現象世界) を示す。
なぜ「1」を抜くのか?
これも古くから討議されていた事です。下記の説明はどれも同じ事を意味していますが、それぞれ違う視点からアプローチしているため、掲載します。
(1) 1=太極(根源の1)を象徴した数値
人間が扱うことが出来る宇宙の数は「50」、だが、その中には、全宇宙の根源である1=太極=人間が直接触れることのできない根源数が含まれていた。故に、根源数は目に見える世界の中には含まれず、不可視の存在ということで、1を抜いた。
(2) 現象界(49)と超越界(1)の区別
2+5=7=陰陽五行 7×7 =49という数値は、天地自然・四季・陰陽が展開する「見える世界」の秩序を示している。つまり、残された「1」は、現象の外にある 不可視の原理 を意味するとし、占筮で用いるのは「現象界(49)」であり、「1」は人知を超えた道として抜いた。
(3) 「1」は天・人・地の枠を超える数
中国古典では「三才(天・地・人)」が世界を示す基本数値であるが、その根底には「1=無形の一体性」があるとした。
⑤ 太極とは
-
「易は太極を生じ、太極は両儀を生ず」とあるように、
太極= 万物が生まれる前の根源的な数=1であり、全宇宙の元となる数字 -
陰も陽もまだ分かれていない状態。
動くことも静まることもなく、すべての可能性が含まれている -
西洋哲学的にいえば「存在の始まり(Being itself)」、仏教でいえば「空」に近い概念
⑥陽=9、陰=6とした理由
陰陽理論(古代中国基本思想)
奇数=動的・能動的・太陽・天=陽
偶数=静的・受動的・月・地=陰
陽は 天・エネルギー
天は果てしなく広がり、光を放ち、動き続けます。
そのため、奇数の最大値は9であり、完全に満ちた動の数です。
9は天の運行を象徴し、止まることなく未来へと展開していきます。
陰は 地・器
地はすべてを受けとめ、育み、安定させます。
6は、六合(天地+東西南北)を現わした数であり、調和数として捉えます。
6は大地の広がりを象徴し、何ものも拒まず包み込む数値です。
天=陽=9 ―― 光と運動の数
地=陰=6 ―― 包容と安定の数
天と地 宇宙のエネルギーと大地の器
この2のあいだに生命が息づき、
その中で万物は循環しながら誕生し、育成し、やがて還っていくのです。
これが古代中国の宇宙観です。
⑦ 乾=216 の理由
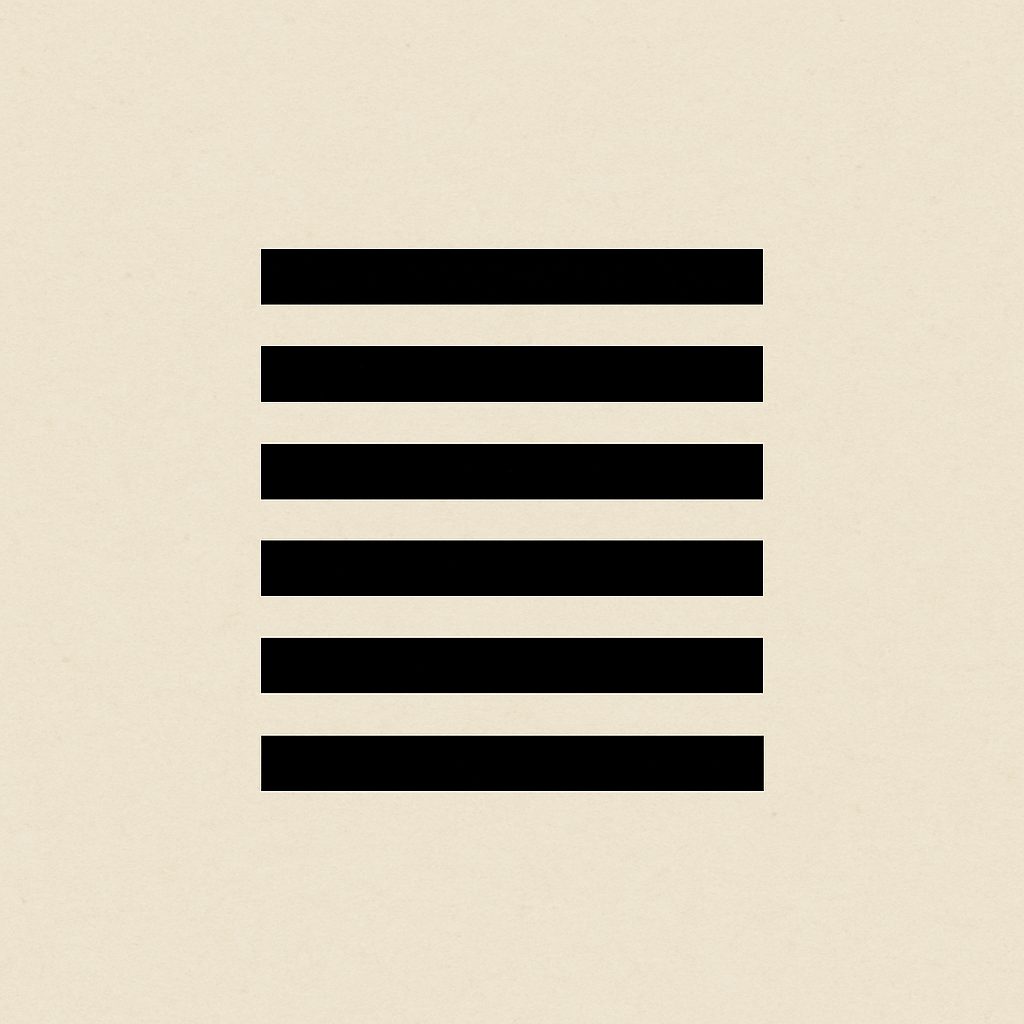 乾卦(☰)は 六爻すべてが陽爻(—) です。
乾卦(☰)は 六爻すべてが陽爻(—) です。
-
陽爻 = 9
-
陰爻 = 6
乾卦は陽爻6本なので:
9×6本=54
54×4=216
一本の爻に全体が宿るという易の思想により、
54(陽爻6本の合計)を四方に広げて 216。
この数字が「陽の力が宇宙全体へ展開した象徴数」になります。
⑧ 坤=144 の理由
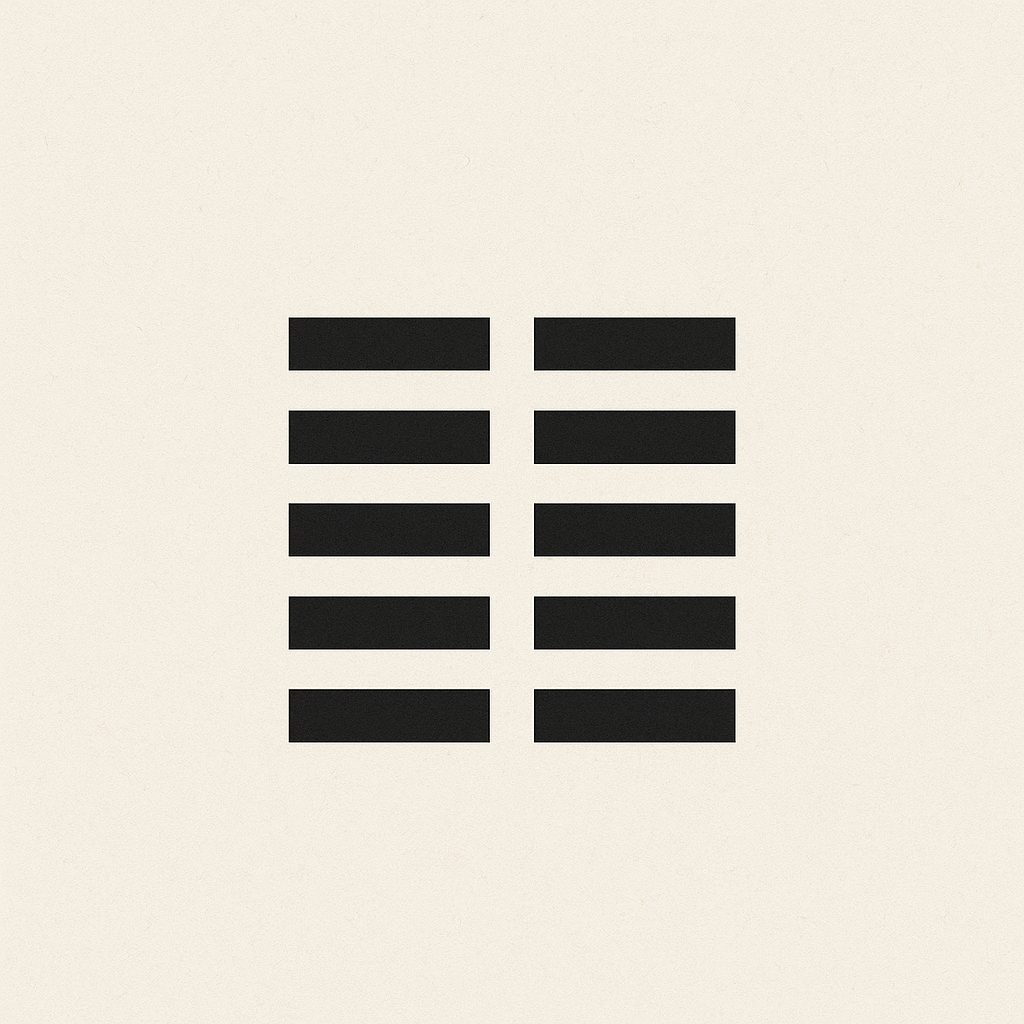 坤卦(☷)は 六爻すべてが陰爻(--) です。
坤卦(☷)は 六爻すべてが陰爻(--) です。
陰爻は 6 で表されるので:
6×6本=36
36×4=144
「受ける力」「安定する力」
36(陰爻6本の合計)を四方に広げて 144。
この数字が 「静かにすべてを抱え込む大地の象徴数」になります。
陽=奇数(動的)、その極が「9(最大の奇数)
陰=偶数(静的)、その極が「6(最小の偶数)
乾(216)+坤(144)=360=1年の日数(360日=古代の太陽暦の基準)
⑨「二篇全体の策は一万一千五百二十あり、これは万物の数に対応する」
「二篇」とは『易経』の上下二巻(上経と下経)を意味します。
本来、易は64の卦で構成していますが、それを天と地、上下の二篇に分けたため、64÷2=32という数字を用います。
360(日数)×32(卦の半数)=11,52
なぜ、64でなくて、なぜ、半数の32を用いたのか?
「64卦」は三爻で構成される「八卦」(☰乾・☱兌・☲離・☳震・☴巽・☵坎・☶艮・☷坤)の8種類で構成されており、これを上下で組み合わせて構成しています。
→ 8 × 8 = 64通り
しかし、上下で反転すると、陰陽的にセットになるため、32組のペア(対)として捉えました。
-
震☳☳(雷)⇄ 艮☶☶(山)
-
離☲☲(火)⇄ 坎☵☵(水)
-
兌☱☱(沢)⇄ 巽☴☴(風)
「0(無)」と「1(太極)」――東洋思想とAIの未来
東洋における「0」と「1」
西洋やインドでは「0」は数学的な記号として数の体系に組み込まれました。
一方、中国思想には「0」という記号は存在せず、その代わりに「無」や「空」という概念で語られました。
『道徳経』には「天下の万物は有より生じ、有は無より生ず」とあります。
ここでの「無」とは、単なる「何もない」状態ではなく、すべての可能性を孕んだ根源的な場。後に仏教では「空」として展開し、固定的な実体はなく、あらゆる存在は縁起によって変化するという理解へとつながりました。
したがって、東洋における「無」は欠如ではなく、むしろ潜在的な豊かさを象徴しています。
やがて「無」から最初に立ち現れる「有」が「太極=1」です。
ここから陰陽(二)、四象(四)、八卦(八)へと展開し、宇宙の秩序が広がっていきます。
つまり、易経において「数えること」は「1」から始まりますが、その背後には常に「数える前の状態=無」があるのです。これはインドで数学的な「0」が生まれる以前から、中国思想において「ゼロ的概念=潜在の無」が存在していたことを示しています。
AIと人間――「49」と「1」の役割
AIと人間は、ともに「49の世界」を扱います。
数字を読み、データを整理し、パターンを見抜く――これはAIが圧倒的に得意な領域です。人間も経験や知識を積み重ねて「49」の世界を生きていますが、両者には決定的な違いがあります。
-
AIの強み:計算・整理・最適化(49を極める)
-
人間の強み:直観・創造・共感(1の気配を感じ取る)
AIはどれほど計算を極めても「根源=1」に触れることはできません。夢を見たり、答えのない問いに悩んだり、意味を見出すことはできないのです。
一方で人間は、直観やひらめき、芸術や物語を通じて「1の気配」に触れ、それを新しい創造へとつなげることができます。
「人間にしかできないこと」とは?
「なぜ生きるのか」「この苦しみに意味はあるのか」――。
AIはいくらデータを分析しても、こうした根源的な問いに答えを与えることはできません。そのため、問い続けることそのものが、人間の尊厳であり、創造の源ではないでしょうか?
私達は、AIに「49の処理」を委ねながらも、「1を感じる力」を最大限に発揮していくことが求められるていくでしょう。
共同作業の具体像
-
経営・戦略
AIは市場データを瞬時に分析し、人間は社会の空気を読み取り、人々が共感できる未来像を描く。 -
創造活動
AIは無数のアイデアを提示し、人間は「美」や「意味」を感じ取り、魂を揺さぶる一点を選ぶ。 -
医療・科学
AIは身体を診断し、人間は心を癒す。 -
教育
AIは学習履歴から最適なカリキュラムを生成し、人間は学ぶ喜びを伝える。
「0」から「1」の生成
しかし、近年の生成AIは「人間に寄り添う表現」が出来るようになっています。
人間がAIに負けない「1」を引き出すにはどうすればよいのでしょうか。
そのヒントには、東洋思想の「0」という概念が大きな意味を持っていると思うのです。
西洋数学における「0」は、数量的な記号ですが、東洋思想の「無」や「空」は、「何もない」のではなく、可能性を孕んだ源泉として理解されています。
現代のAIは、西洋数学の理論や統計的学習を基盤に設計されていますが、哲学的な「無=源泉」は、直接モデル化しているわけではありません。AIは膨大なデータを処理し、そこから新しい組み合わせを生成することができます。したがって、「1以降」の世界―すでに与えられた情報を展開・最適化することには非常に優れています。
しかし、人間が体験する「0から1が生まれる瞬間」―まだ形のない直観や、意味づけの始まり、存在に新しい価値を見出す感覚―これはAIの計算プロセスとは異質の営みです。AIは過去のデータの延長から新しいアウトプットを生成できますが、「根源的な意味の誕生」を経験するわけではありません。
「0から1の生成」こそが人間の本質ではないでしょうか?
AIとの協働する未来
それでは、「0を感じる」とはどんな体験でしょうか。
1. 恋愛における「0」
好きな人に気持ちを伝える前の、不安や沈黙。
結果が見えない“空白”の時間こそが「0」であり、そこから関係が始まると「1」が立ち上がります。
この空白の時間を飛ばして安心を求めるばかりでは、0から1へのエネルギー転換を経験できません。
2. キャリアにおける「0」
就職や転職のタイミングで、「次に何を選ぶべきか分からない」という状態。
その不安や迷いの中から、新しい方向性(1=意味・役割)が芽生えていきます。
もし迷いをすぐに他人やAIの答えで埋めてしまえば、自分自身の内側から湧き上がる「1」の力を鍛える機会を失ってしまいます。
3. 創造における「0」
真っ白なキャンバスや、まだ一文字も書かれていないノート。
「何もない」からこそ、最初の線や言葉を置いた瞬間に新しい世界が始まります。
その初動のひと振りを、自分の力で生み出すことこそ大切です。AIに答えを委ねすぎると、「0から1を生み出す感覚」が育たなくなってしまいます。
告白する前の沈黙、次の道が見えないときの迷い、真っ白なノートを前にした創造の瞬間。
どれも不安定で落ち着かない状態ですが、その状態から、「1=意味」が立ち上がるのです。
AIは無限に計算できても、根源に触れることはできません。
人間は有限でありながら、無限を感じ取り、0から1を生み出すことが出来るのです。
それでは、どうすれば「0から1を生み出す感覚」を磨くことが出来るのでしょうか?
空白をそのまま受け入れること、答えの出ない問いを抱き続けること、初動の不完全さを楽しむこと、そして、科学の発展前に記された古典や自然に潜む秩序に耳を澄ますこと!
つまり、まだ意味を持たない段階から、新たな意味を立ち上げる体験を重ねていくしかないような気がします。
時間がかかるかもしれませんが、この一見無駄に見える、コスパもタイパも悪い事でしか、人間性を磨く方法はないような気がしています。