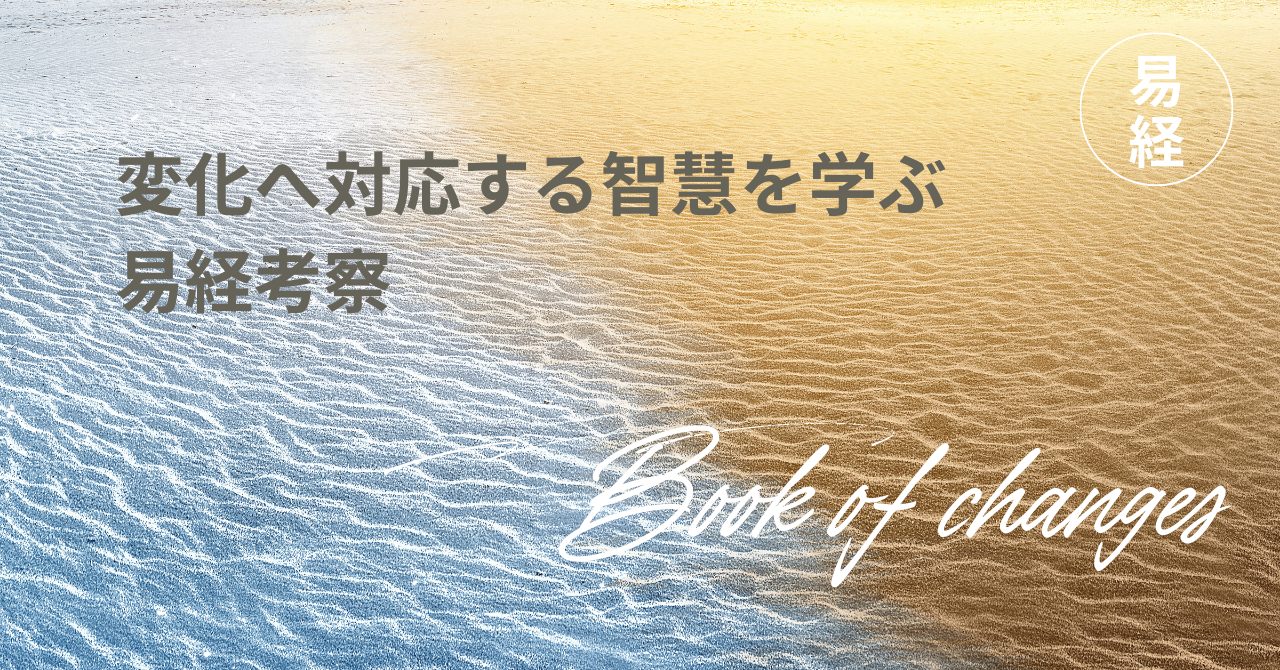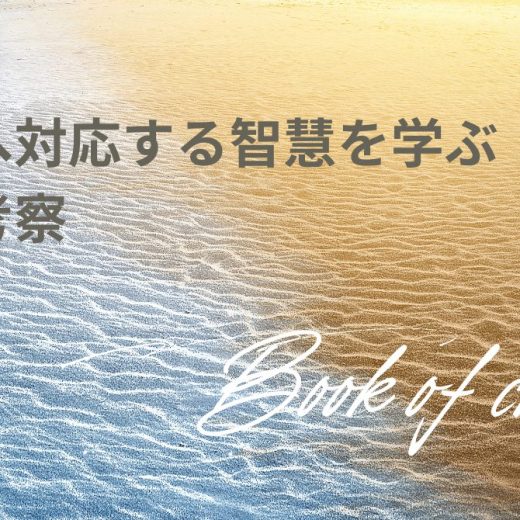天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。
「天は高く尊く、地は低く広がる。これによって、天地の秩序が定まる。
高いものは高く、低いものは低く、その配列によって貴賤の位が定まる。
動くものは動き、静かなものは静かにあり、それぞれの道理に従う。
剛は剛として、柔は柔として、それぞれの性質をもって万物を調和させる。
同じ性質を持つものは集まり、類は類をもってまとまる。
そこから吉と凶が生じる。
天においては、すべてが象(かたち)となって現れ、地においては、具体的な形を成す。
このようにして、世の中の万物は、常に変化し、移り変わっていくのである。」

天地の秩序と人間社会
天は尊く、地は低い。これによって、乾(天)と坤(地)の位置が定まる。
高いものと低いものが順序立てて並び、貴いものと賤しいものの位が定まる。
動くものは動き、静かなものは静かにあり、それぞれの道理に従う。
剛は剛として、柔は柔として、それぞれの性質をもって調和する。
似たものは自然と集まり、類は類をもってまとまる。
そこから吉と凶が生まれる。
天においては、その兆しが印され、地においては、実際の形となる。
この自然の道理を学べば、
万物の変化が目に見えるようになり、
変化のタイミングをつかむことができるのだ。
農耕民族の視点から見る「天地」
中国文明は、黄河・淮河・長江という三本の大河の流域で発展した。
つまり、古代中国の民族とは、泥水にまみれた田を耕し、土に向かい合って生きる農耕民族である。
彼らにとって「土」は、すべての生活の基盤である。
遊牧民は土地に縛られず、 近代以降の工業社会の人々は、環境が悪化すれば新たな土地へ移動する。
しかし、農耕民はそうはいかない。 生まれ育った土地に根付き、先祖代々の地で生きることが人生だったのだ。
戦乱や天候不順でやむを得ず土地を離れることはあっても、それは異常事態である。
そのため、どこにいようと、人は出身地というルーツを持ち続ける。 それは、単なる地理的な故郷ではなく、天地とつながる深い意味を持っている。
大河の氾濫と文明の発展
三本の大河は、古代中国の農耕民にとって恵みであると同時に脅威でもあった。 特に黄河は「中国の憂い」とも呼ばれ、たびたび氾濫し、広範囲にわたる被害をもたらした。 しかし、この氾濫こそが、農耕社会の存続に不可欠な肥沃な土壌をもたらした。
洪水は、土壌を豊かにする一方で、人々の生活を破壊した。
そのため、農耕民は氾濫を予測し、治水を行うことが必須となった。 こうして、自然を制御するための技術が発展し、組織的な社会が形成されていったのである。
天体観測の必要性
農耕社会において、洪水は天候と深く関わっていた。
雨の降る時期や気温の変動を予測するために、古代中国の人々は天体観測を行うようになる。
洪水が発生する時期を知るためには、暦が必要であった。 太陽の動きや星の配置を観測し、季節の変化を記録することで、農作業の適切な時期を決めることができた。 こうして、古代中国では天文学が発展し、それが陰陽五行思想や占星術にもつながったのである。
支配者と被支配者の誕生
洪水を防ぎ、農業を安定させるためには、大規模な治水工事が不可欠であった。
しかし、それを実行するには、多くの労働力と組織的な指導が必要であった。
こうして、天体観測により暦を制作し、治水を指揮する指導者が崇められ、次第に権力を持つようになった。
彼らは天体観測や治水技術を駆使することで、天から命を預かる者、「天命を受けた王」として統治を正当化した。
一方で、農民は土地に縛られ、収穫を納めることで支配者を支える存在となった。
こうして、農耕社会では支配者と被支配者の階層が生まれ、長い歴史の中で王朝が交代していくこととなった。
『天地』の思想と農耕民の精神
易経では、天が高く尊く、地は低く卑しく位置付けられ、この秩序によって天地が安定すると説く。
天地の差は上下や貴賤の差を生み、動と静、剛と柔という対比が定まる。
農耕民は、この思想を深く理解していた。それこそが、古代中国において自分達の生活を守る秩序だったのだ。
彼らにとって天は規律を示し、地はその規律の中で生きる場を提供した。
こうした天地の秩序に従い、自然の摂理に基づいて暮らすことで、安定した生活を築いたのである。
さらに、同じ性質を持つものが集まり、社会秩序が形成される。
他民族国家中国では、同族(同じ家系の者)、同じ民族が集まり、同族が単位となり社会秩序が形成されたことを意味する。
人々は自然の変化を観察し、その吉凶を見極めて生活を営んだ。
農耕社会における「天地」の観念は、このように自然の秩序を反映し、人間社会のあり方を規定する根本原理となったのである。
「天地」の思想と農耕民の精神
大河の氾濫は単なる災害ではなく、文明の発展を促す原動力でもあった。 農耕民にとって、天地とは単なる自然ではなく、生活そのものであり、社会の根幹であった。
彼らは土とともに生き、天の命を受けた支配者が制定した暦を読み、自然と共存することで文明を築いた。
その精神は、「天と地の調和」を重んじる儒教や道教の思想にも受け継がれ、 現代に至るまで中国文化の根底に流れ続けている。
「天尊地卑」の本当の意味
決して「地が卑しい」という意味ではない。
白川静氏によると、「卑」という字は、小さな匙(さじ)を手に持つ形から生まれた。
もともとは「空間的な幅が小さい(低い)」という意味があり、後に身分の低さを表すようになった。
つまり、生まれた土地から離れることのない狭さである。
一方で「尊」は、酒樽を両手で捧げて神前に供える形を表す。つまり、「尊」は酒樽を意味し、
大自然や天神に酒を捧げ、それによって地で恩恵を受けるという行為を示しているのです。
暦を読み、祭祀を行う。それが支配者の役割であり、天を対象としているため、空間的な幅が大きい。
天の支配者とは、空間的束縛のない状態である。
天地の秩序とは、単なる上下関係ではなく、天と地が互いに関わり合い、調和を成すことが重要であることがわかります。
変化を見極める智慧
易経では、変化には必ず前触れがあると説いている。
ここでの前ぶれポイントは、
似たものは自然と集まり、類は類をもってまとまる。
そこから吉と凶が生まれる。
である。それこそが秩序だと言っているのだ。
確かに平和・安定とは、「自然に集まった似た者」と一緒に暮らすことかもしれない。
今の時代を見てみよう。
多くの人が自由に情報を交わし、交流する時代。
自然に「似た者」と出会うことすら難しい。
自然に集まった「似た者」との社会が、事の吉凶を生じるのであれば、その社会の崩壊は凶である。
時代の大きな流れ、動きを乗り越えるには、
自然に集まった「似た者」同士の関係性構築こそ、一つのヒントなのかもしれない。