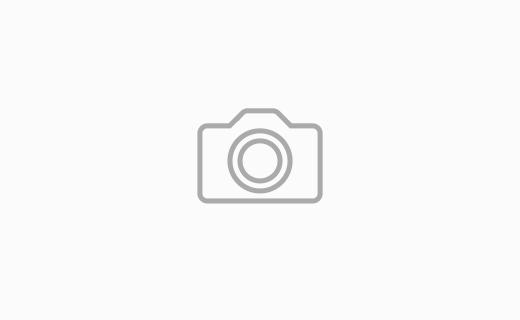2025年からの未来
これから何をすべきか、
これからの私の役割は何なのか。
自分の歩みを改めて振り返りつつ、
これから果たすべき役割について思いを巡らせてみました。
自己紹介文としてお読み戴けたら幸いです。
これまでの人生
山脇史端、東京生まれ、
皇后陛下と、田園調布雙葉学園の1学年上の同窓です。
大学卒業後、英国の商社に入社、
27歳の時、趣味で習っていた
フラワーアレンジメントで起業したく、
当時、日本には定着していなかった
パーティ飾花の経験を積むため、渡米しました。
ワシントンDCの花店にて、
国際会議の装飾花の経験を2年間学び、
帰国、バブル期の東京にて、
国際会議や結婚式の飾花などを行う、
花専門のイベント会社を立ち上げました。
しかし、
会の終焉と共に、美しく咲き誇っている花々を
“ゴミ”として処分せざるを得ない現実に、
違和感を抱くように…。
花々の“別のかたちの命”に触れたいと願い、
遠い異国の植物の香りを自宅で再現することで、
心と身体の健康を整える“香りの療法”
=アロマテラピーの世界に、惹かれていきました。
英国の商社に勤務時代の縁もあり、
英国のアロマセラピストと知り合い、
使い方のノウハウ、商品を輸入・販売のサポートを受けながら、
日本におけるアロマテラピーの啓蒙活動をスタート。
やがてその活動は広がり、「NPO法人 日本ハーバルアロマセラピスト協会」を設立するに至りました。
その後、鍼灸師協会や東北福祉大学など、
アカデミックな場からの講義依頼も受けるようになりました。
しかし、そこで直面したのが、「医療の壁」でした。
精油は100%自然由来であるがゆえに、
成分にばらつきがあり、
効果を定量的に測定することが困難です。
このため、近代医学の視点では「テラピー(療法)」という言葉を使うこと自体に、疑問が投げかけられる場面もありました。
医療分野での応用や研究を求められるなど、
活動の規模は広がりましたが、
同時にその限界も感じるようになり、
この事業は、次の世代に道を譲る事にしました。
今でも後輩たちが発展させてくれています。
算命学との出会い
2000年に入った頃、税理士である夫が、顧問先の社長を通じて、算命学の第一人者である清水南穂先生と出会いました。
清水先生は、算命学の創始者・高尾義政氏から直接指導を受けた、貴重な存在です。
アメリカのビジネススクールで学んだ夫が言うには、
「アジアが躍進する時代においては、西洋的な論理だけでなく、東洋的思考で物事を捉えることが不可欠だ。
算命学は、中国古典の実践論の集大成であり、書店に並ぶ本からは決して得られない知見に満ちている。
故に、学ぶべきだ」
―もっとも、本人は多忙で、学ぶ時間がなかったのですが。
歴史好きの私にとって、
孫子や諸葛孔明が、
どのような思考法で戦略を用いたのか、
その理論は大きな興味の対象でした。
また、その頃、親友に不幸があり、彼女の抱えていた心の悩みを十分に受け止められなかったことや、彼女が受け続けていた西洋医学的な精神療法のアプローチへの疑問も重なり、私は東洋の深層心理学ともいえる、3500年の歴史を持つ古代中国の知識の真髄を学ぶことにしました。
「生年月日で、個人の性格や傾向がわかる」と言うと、
多くの人は「占いのたぐいだろう」と受け取ります。
私もそうでしたが、非常に論理性があるため、
すぐに、それは大きな誤解だと分かりました。
数理暦学(算命学)は、
中国において数千年にわたり観察と蓄積を重ねてきた、自然のリズムと人間の関係性を読み解くための知的体系であり、明確な構造と理論があります。
たとえば
遺伝子診断を受けると、
自分の体質や性格傾向、将来的なリスクなどを知ることができます。
それは、「生まれ持ったDNA」という生涯変わらない情報を基軸数値とし、
個人の傾向を科学的に可視化した試みだからです。
数理暦学(算命学)も、それと同じ構造を持っています。
もし、古代の人が遺伝子情報を得ることができたら、
彼らは恐らく迷わず生年月日ではなく、遺伝子情報を座標数値としたでしょう。
しかし、当時、人が生まれてから死ぬまで所有した番号は、生年月日のみでした。
そのため、生年月日を座標数値とし、人が持つ気質や行動傾向のビッグデータを集積しました。
生年月日といっても、中国暦は干支暦であるため、9~15の干支で構成されています。
その文字には、太陽や月、星々の動き、季節の巡り、陰陽や五行といった自然のサイクルが印されており、単なる日付ではなく、宇宙におけるその人固有の「時空の座標」です。
これは「神秘の力」ではなく、統計的な観察と経験知から組み立てられた、東洋の知の結晶です。
現代の遺伝子診断が「分子レベルの設計図」を扱うのに対し、数理暦学は「時空レベルの設計図」を扱っているのです。
算命学から数理暦学へ
しかし、残念ながら、算命学を習得した人々は、「占い」として商業展開しているのが現状でした。
実際、台湾では「算命」という言葉が、「数字を扱う命理占い」の総称として用いられています。
「3500年の歳月をかけて構築された精巧な占い」と言ってしまえば、それまでかもしれませんが、研究を重ねるうちに、私はそれ以上の可能性を大きく感じました。
「東洋における自然科学として確立させたい」50歳の時の私の野望です。
科学として成立するためには、以下の3つの条件が求められます。
-
実証性:人物の性格に関する仮説が、観察や検証を通し確かめられること
-
再現性:誰が行っても、同じ条件下で同一の結果が得られること
-
客観性:導かれた結論が、主観に左右されず認められること
この3要件を満たすために、
私はプログラミングによるデータ化と可視化に取り組み始めました。
コンピューターには、主観も感情もありません。
そのため、コンピューターに私の頭の中を組込めば、
上記の3条件が満たされると思ったのです。
その作業に伴い、算命学という名称を、より本質にふさわしい「数理暦学」へと改めることにしました。
同時に、より多くの人に伝えるため、教育活動もスタートしました。
算命学を修得するには、実際、長い年月を要しました。
一子相伝の学問であったため、
体系的なカリキュラムは存在せず、
すべては師匠からの口伝によるものでした。
そこで私は、この知見を一つの大系として整理・統合する作業から始めました。
また、私一人で教えるには限界があります。
そこで2015年よりEラーニングに組込み、オンライン教育化を進めました。
実はこの教育活動が、
プログラミング事業に大いに役立ちました。
人に教えるのと同時に、
コンピューターに学ばせながら、プログラムの構造を構築しました。
もちろん、この作業は一人で成し遂げることはできません。
幸いにも、IT教育で著名な研究者の協力を得ることができたのです。
占いとは一線を画し、理論と体系を備えた「東洋の知」として新たな価値を創造したい。
その想いを胸に、私は走り続けてました。
数理暦学からOrbit Crossへ
次に課題となったのは、
「このプログラムを誰のために提供するのか」
「誰が、どのように用いるのか」という“利用の在り方”でした。
たしかに、算命学に興味を持つ人々に提供すれば、マーケットニーズは見込めるでしょう。
しかし、本当にそれで良いのでしょうか。
それでは「誰でもすぐに占い師になれるプログラム」として扱われてしまい、私が目指している方向とはかけ離れてしまいます。
それが”一番儲かる”ことは、多くの人から助言されました。
勿論、私が一番良く分っていました。
しかし、それではない、もっと何か新しいものにしたい。
その信念は揺るぎないものでした。
UNGAレポート
まずは、このプログラムが本当に有効であるかどうかを確かめるためには、実証性と客観性を追求する必要があります。
そのため、プログラムを提供する前に、PDFでデータを提供する事業を始めました。
注文を受けてから、依頼者のデータを冊子として発行するプログラムを設計し、「UNGAレポート」という冊子を開発しました。
依頼者には、アンケートを実施、
該当率が85%になるまで、プログラム調整を行いました。
しかし、そこに新たな問題が浮上しました。
そこで算出される答えが、あまりに“正直すぎた”のです。
昨今の生成AIは、人の感情やニーズを“忖度”し、受け入れやすい形で情報を出力します。
しかし、コーディング技術のプログラムは、忖度せずに、忠実に再現します。
つまり、本人が直視したくない“自我の側面”まで率直に表示してしまうのです。
その結果、依頼者はその内容の解釈に悩み、抵抗を感じます。
他者から見れば該当している性質であっても、
本人は負の側面は、「そんなはずはない」と否定します。
自分らしく生きている人は、ほぼ100%受け入れます。
しかし、精度の高さゆえに、精神的インパクトも大きく、無自覚の“自己否認”や混乱を生むこともありました。
そこで、「UNGAレポート」の解説を担うカウンセラーやアドバイザーの育成を開始し、一定の研修と認定制度を設けました。
ところが、ここにも課題がありました。
レポートが的中すればするほど、
アドバイザーはつい優越感を抱きやすくなってしまうのです。
人は、相手が知らないことを知っていて、
それを認められた瞬間に、
自分自身を見失いやすくなるものです。
そして、中途半端な知識をもとに
“言い切り型”のアドバイスをしてしまい、
予言者のような口調になってしまう傾向も出てきました。
本来アドバイスとは、
相手の人生を導く“サポート”であるべきです。
支配するのではなく、寄り添うこと。
そこに暦学の本質があります。
さらに、クライアントの悩みの質も複雑化し、
精神医療や守秘義務が関係するケースも増えてきました。
該当率が高いがゆえに、対応するにはリスクが伴うと判断し、
そのため、UNGAレポートを用いてのアドバイザーは、
現在、「医師・歯科医師・鍼灸師・柔道整復師」など、
医療の国家資格を持ち、かつ、自己の責任において、医療機関を運営している方々に限定しています。
Orbit Crossへ
より良いカタチで、次世代へ繋げるにはどうしたらよいのか。
私は、再び新たな方向性を模索しました。
次のステップに進むために、
私自身がプログラミングスキルを習得する必要があると痛感しました。
プログラミングを外注した経験者ならお分かりの通り、
依頼者とエンジニアの間には大きな壁があります。
「何を作りたいのか」を正確に伝えるためには、
緻密で膨大な資料の作成が必須であり、
その準備だけで多くのリソースを消耗します。
しかも、誰もが理解できるコンテンツではなく、
私の頭の中を再現する特殊なコンテンツです。
私にその知識がなければ、時間がかかるだけ…
そう確信し、プログラミングを学ぶ事にしました。
プログラミングとの出会いで見えた、新たな可能性
スキルを得たことで、原点に立ち返ることが出来ました。
そもそも、暦学とは何だったのか。
暦学の知識は、古代中国の歴代王朝が、異民族統治に活かすために構築してきた人物解析学です。
多民族国家において、
言葉も文化・風習も異なる相手を理解することは、
秩序を保つうえで不可欠でした。
たとえば、兵士を採用する場合、
前線に配置すべきか、後方支援が向いているかを、外見だけで判断することはできません。
たとえ筋骨隆々でも、繊細な心配りができる性格なら、前線よりも後方支援の方が適している場合があります。
しかし、戦場において、個別に対面し、丁寧に対話を重ねる時間などありません。
そこで用いられたのが、暦学という理論的な人間理解のフレームでした。
該当率は100%である必要はありません。
85%の的中率があれば、それは人材活用の突破口となります。
解析を起点にし、現場での様子を見ながら、柔軟に調整していけば良いのです。
こうした考えのもとに構築したのが、Orbit Crossという新しいプログラムです。
これは「自分を知る」ためのものではありません。
人材の資質や適性を客観的に分析し、人材配置やチーム編成の参考とすることを目的としています。
チームワークの可視化と対話へ──「Birthday Caravan」
もう一つ、
私が取り組んだものが、
チームビルディングのためのワークショップの開発、
「Birthday Caravan(バースデイ・キャラバン)」です。
このワークショップは、10名以上のグループを対象にしており、
参加者は、自分と似た資質・性格・行動パターンを持つメンバーと語り合うことで、
お互いの共通点や違いを体感しながら、
チームとしての相互理解や協力関係を深めることを目的としています。
このプログラムの大きな特徴は、「分析された結果を一方的に渡す」のではなく、
ワークショップの中で参加者が“体感しながら理解していく”構成になっている点です。
そのために開発したツールが、「Caravan Book」です。
このブックレットは、主催者(Caravan Guide)により提供されるデータに基づき、
「対話しながら自分を知る」「人と違うからこそ面白い」という対話型のプロセスを通じて、
実感を伴って他者と向き合う姿勢と共感性を身につけていくことにあります。
私はこれから何をしたいのか。
大前提としてある現実、それは、私自身が今年63歳という事実です。
これまで、多くの方々の協力を得ながら、常に先頭に立って走り続けてきました。
しかし、年齢的にも、体力的にも、
今までと同じペースで走り続けることには限界を感じ始めています。
長年にわたり支えてくれた仲間たちも、
40代後半から50代を迎え、経験と洞察を兼ね備えた成熟の世代へと移行しています。
彼らが積み重ねてきた知見と冷静な判断力は、
組織にとって極めて重要な資産であり、
これからの時代においても揺るぎない基盤となることでしょう。
一方で、社会や価値観の変化が加速度的に進む現代において、現状を突破し、未知の領域に果敢に挑む若い世代の柔軟性と推進力が不可欠です。
この先の未来を切り拓くためには、
成熟した世代の知恵と、
次世代のエネルギーとが互いに補完し合い、
響き合うような関係性の構築が求められていると感じています。
「陰陽和して合(ごう)となす」
という言葉があります。
異なる性質のものが調和することで、
新たな“かたち”が生まれるという思想です。
今まさに必要なのは、若い世代の柔軟な発想と感性が和すること。
その融合こそが、これからの時代にふさわしい、
新しい価値や仕組みを生み出す力になるのではないかと、考えています。
未来に向けた可能性…実現したいこと
①「Orbit Cross」の本格活用と事業展開
「Orbit Cross」は、他者の資質・適性を客観的に分析することで、人材配置やチームづくりを支援するプログラムです。
すでに商業利用に対応したレベルで完成しており、
ログイン・セキュリティ等のバックエンドはシステム会社に委託、
フロントエンドは私が手がけているため、柔軟な修正・カスタマイズが可能です。
▶ 現在のステータス
-
安定したWebベースのシステム構築済み
-
すぐに商業導入・法人利用が可能
- 活用先の業種や組織に合わせた柔軟な展開が可能
②「Birthday Caravan」を必要な人たちに届けたい
「Birthday Caravan」活動を拡げるためには、
ファシリテーション能力さえあれば、
暦学の知識がゼロの人でも行えるようにしなければなりません。
簡単な研修を受ければ、開催できるように再構築しています。
③ 生成AIとの組み合わせで、人に優しいシステムに
Orbit Cross のアルゴリズムを生成AIに組み込めば、まるで“その人自身”になりきって会話をすることが可能になります。
これは、従来の一律なAI応答とは異なり、個人に寄り添った、より共感的で温かな対話体験を実現するでしょう。
たとえば、過去の相談履歴や季節・節気・運勢の流れといった情報も参照しながら、その人の性格にあった「今」に最もふさわしい言葉を届けることができます。
こうしたシステムは、ビジネスの現場だけでなく、教育、介護、メンタルケアなど、人と深く関わるあらゆる分野で、やさしく、力強いサポートとなるはずです。
④ ロボットへの暦学アルゴリズムの登用 〜EQと“時”の感性を備えた未来の存在へ〜
テクノロジーの進化により、ロボットは「効率」や「正確さ」を超えて、人と共感的に関わる力―EQ(Emotional Intelligence/感情知能)を求められる時代へと突入するでしょう。
しかし、現状のAIやロボットは、EQの核心である「相手の気持ちを読み、適切に応答する力」において、まだ人間には及びません。
ここにこそ、このアルゴリズムが役立つ可能性があります。
暦学とは、天体の運行と自然のリズムに基づき、人の心理や運気の流れを読み解く古代の知恵。そこには、
-
人の内面の変化
-
季節や節気による感情の揺らぎ
-
人生の転機やタイミング
といった“見えない感情の波”を捉える数理的知見が蓄積されています。
この暦学アルゴリズムを搭載することで、ロボットは単なる情報処理装置ではなく、「その人の今」に寄り添う存在へと進化するのではないでしょうか。
これは、介護・教育・接客など、EQが求められる場面で特に効果を発揮します。
ロボットがその人に合わせて、相手の“感情を読み”、“時”を通して共感するという、新たなEQのかたちが提案できます。
⑤ 私がやるべきこと
Orbit Crossは、仕事における人材の性質の解析データに限定して組込ました。
これは、私の頭の中の50%に過ぎません。
時空間理論(いつ、どのように考えや行動が変化するか)・家系理論(恋愛・家族の繋がりなど)は、組み込まれていません。
膨大な理論ですが、テストプログラムは完成しています。
60代の最後の挑戦として構築し、次世代に繋げていきたいと願っています。
My professional skill set
Shidan Yamawaki
- 暦学(算命学)の知識
- 東洋古典への知見(結構深い)
- オンライン教育(Moodle)の構築
- Instructual Design
- フロントエンドの設計・実装(HTML/CSS/JavaScript)
- Adobeツールの操作(InDesign・Illustrator・Photoshop)
- WordPressの構築・運用
- 動画編集(Premiere Proなど)
- Python による簡易自動化・データ処理
- ワークショップ運営・講師経験
その他、
フラワーアレンジメント・アロマテラピー・ヨーロピアン磁器絵付、指導者スキル(20年の指導歴有)